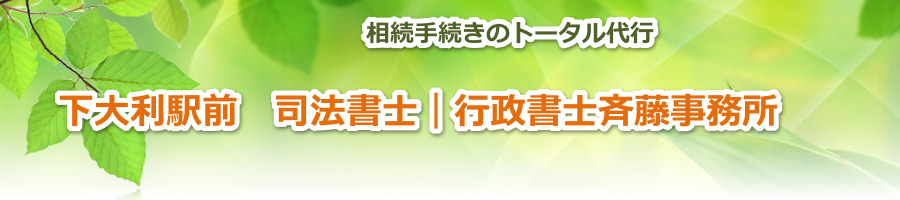相続のお悩み相談

面倒で複雑な相続の手続きは西鉄下大利駅西口広場前の斉藤事務所にご依頼ください。
司法書士・行政書士のW資格でほとんどの相続手続きを1か所で行っています。
数多くの相続手続きの経験があり1か所で手続きが完了しますから、スピーディーで安心できる手続きです。
料金は金融機関等が行う相続手続きの代行の場合の半額以下のリーズナブルな設定です
相続手続きで当事務所が行う事ができること
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍の収集による相続人調査
相続財産の調査・簡易査定
銀行・ゆうちょ銀行・証券会社等の残高証明書の取得
遺産分割協議書の作成
法務局で法定相続情報一覧図の取得
不動産の名義変更(相続登記)
銀行の解約・証券会社の手続き
各相続人の口座への配分金の送金(相続人の間であまり交流がない場合)
その他の名義変更等の相続に関する一切を代行します
相続税の申告が必要な方に税理士の紹介
不動産の売却が必要な場合の不動産業者の紹介
その他 遺言書作成 家族信託 生前贈与 相続放棄 の無料相談も承ります
西鉄下大利駅西口降りてすぐの便利な立地
福岡県大野城市下大利1−13−8
下大利駅前ビル105
司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号
無料相談・問い合わせ
TEL. 092-400-7600
e-mail saitou-office@beetle.ocn.ne.jp
相続に関する無料相談
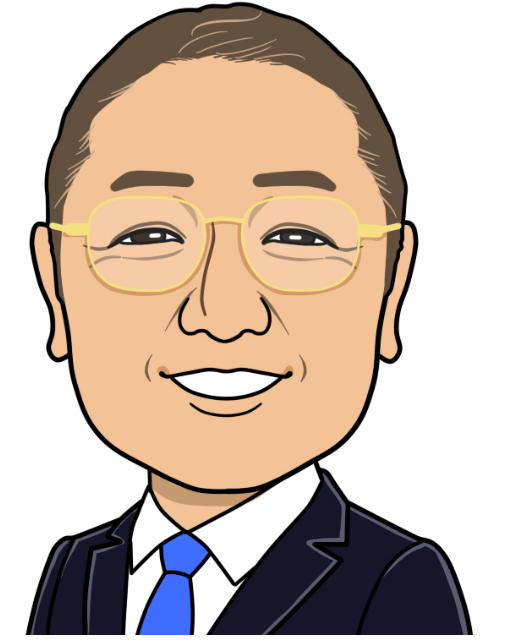
時間を気にせずに無料相談ができます
各種相談種類
| 相続開始後の手続き | ||
| 相続手続き全般 | 相続人調査 | 相続財産調査 |
| 相続放棄 | 遺産分割方法 | 遺産分割協議書作成 |
| 相続登記 | 預貯金・証券等の相続手続き | 相続不動産の評価 |
| 相続開始前の手続き | ||
| 家族信託 | 遺言書作成 | 生前贈与 |
| 不動産親族間売買 | 成年後見 | 相続税対策 |
| 不動産の取扱い | 音信不通の相続人調査 | |
慣れない面倒な相続手続き
相続を経験された方が「前回の手続きが大変だったから、今回はおたくに頼みます」とよく来所されます。遺産分割の協議で揉める場合は当然ですが、円満相続の場合も相続手続きは次のような理由で面倒です。
・何度も経験することが無く、慣れてないこと
・一人で勝手に進めることができない
・短い期間で手続きを終えなければならないことが多い
・遠くの役所から明治・大正時代に作成された戸籍を取り寄せる必要も出てくる
・全国に居住する相続人から実印を押した書類や印鑑証明書を取りまとめる必要がある
・預貯金の解約、不動産、車の名義変更等一つ一つに戸籍や書式をそろえて申し出る必要がある
また相続手続きでは相続放棄・相続税申告・遺留分請求など期限がある手続きもありますから、時間に追われるあわただしい作業となります。定められた期限が到来してしまったらその後の手続きを有利に進めることが出来なくなってしまうおそれもあります。
相続手続きでやるべきことは各ご家族により状況は違いますので、まず無料相談をご利用になり、相続手続きの流れ・やらなくてはいけないことをご確認ください。
当事務所の相続手続きの強み
司法書士・行政書士の資格がありますので、相続に関するほとんどのことが当事務所一か所でスピーディーに完了します。銀行・証券会社の手続きも代行します。
相続税の申告が必要なご家族には相続税に詳しい国税出身の税理士さんをご紹介できます。
相続不動産の売却ならマンション売却に強い不動産屋さん・土地建物売却に強い不動産屋さんをそれぞれご紹介できます。
税理士さん・不動産屋さんと連携して動くことが出来ますので、事務の重複を避けることができスムーズに手続きが進行できます。
不動産遺産分割の4つの方法
| 分割方法 | 分割方法の特徴 | メリット | デメリット |
| 現物分割 | 実家の不動産は長男、賃貸アパートは長女が相続するとするように、遺産をそのまま相続する分け方です。不動産を特定の相続人が承継するときは司法書士の相続登記、1筆の土地を数筆に分筆して相続人がそれぞれ相続するには、土地家屋調査士による分筆登記とその後の司法書士による相続登記が必要です。未登記建物を特定の相続人が承継するときは、承継する相続人名義に表題登記を土地家屋調査士がした後、保存登記を司法書士がします。 |
手続きが比較的簡単 |
相続財産の評価が違うので公平性が確保されない場合がある |
| 代償分割 | 不動産を特定の相続人が承継し、不動産を相続しないほかの相続人に不動産を承継した相続人が代償金を払う方法です。不動産は司法書士が相続登記をします。後々の税金トラブル回避のために、遺産分割協議書には代償分割であることを明記しておく必要があります。 |
公平に遺産分割しやすい |
代償金の金額でもめる場合がある |
| 換価分割 |
不動産を売却して売却代金を相続人で分配する方法です。分配の方法や分配割合などは相続人間で自由に決めることができます。宅建業者に依頼して不動産の売却活動をしてもらい、併行して必要により次のような手続きも行います。 |
公平に分配できる |
不動産仲介手数料・測量費用・登記費用・譲渡所得税等の費用が掛かる
誰が名義人(売主)になるかで、名義人に税金支払いの負担がかかる |
| 共有 | 不動産を共有の登記にしていたいときは司法書士が共有の相続登記の手続きをします。 | 公平性がある | 問題の先送りとなる |
遺産分割協議書の役割
遺産分割協議書の役割
相続人間で協議がうまくまとまれば、遺産分割協議書を作成することになります。 この遺産分割協議書は、不動産の名義変更では必要書類となり、預貯金や自動車等の各種名義変更の際には、 証明書としての重要な役割があります。また、書面を作成しておけば後々のトラブルの防止になるとともに、いざというときの証拠にもなります。
遺産分割協議書の作成はどこに頼むか
権利義務に関する書類の作成は弁護士、行政書士の業務範囲となっています。ただし、相続登記のために法務局に提出する書類として遺産分割協議書を作成する場合には司法書士も作成することができます。
当事務所の代行サービス
相続専門の当事務所が法務、税務等の問題をチェックしながら遺産分割協議書を作成します。まずは気軽にお問い合わせください。
手続の流れ
■相続人の確定
産分割協議書を作成するためには、まず相続人を確定しなければなりません。そのためには、亡くなった方(被相続人)の戸籍をたどって確定させますが、戸籍の移動が多いと、その分手間がかかります。また、遠方の場合は、郵送での取り寄せとなるため、多少時間を要します。
↓
■相続財産の調査
相続人が確定したら、相続財産の調査を行います。被相続人名義の不動産、預貯金、有価証券、自動車等を把握することが必要です。多岐にわたる場合は財産目録を作成するといいでしょう。
↓
■相続人間での話し合い
そして、相続人全員で誰がどの遺産をどれだけ取得するのかについての話し合いを行います。相続人間で協議が調わない場合には、家庭裁判所の調停または審判で決めることになります。
↓
■遺産分割協議書作成
話し合いの結果をもとに遺産分割協議書を作成します。遺産が不動産の場合には、登記事項証明書の記載をそのまま転記し、預貯金である場合には、口座の種類・口座番号・残高を明記します。そこに相続人全員が記名押印(実印)し、全員の印鑑証明書を添付します。必要に応じて複数枚作成して各自保管しておくとよいでしょう。
↓
■財産の名義変更
遺産分割協議書が完成したら、その内容に従って財産の名義変更を行います。不動産であれば相続登記が必要となり、預貯金ならば口座を解約の上現金化、有価証券であれば名義書換を請求します。なお、車の場合は陸運支局にて移転登録申請を行います。
↓
■業務完了・手続費用清算
当事務所の相続手続き費用
相続手続きは各ご家庭によりなすべき手続きは異なります。
事前におおよその費用をご提示します。
金融機関が手掛ける相続手続きサポートの半額以下に収まります。
相続手続きは知識がない中で一から始めるには大変な作業です。専門家に代行してもらうのも一つの方法です。その場合気になるのが費用です。
金融機関・相続手続きセンター等が代行する場合の料金
相続手続きは範囲が広く、たくさんの資格者の関与が必要になることもあり、金融機関・不動産業者・FP・士業などが窓口となり、専門資格が必要な部分は司法書士・税理士・土地家屋調査士等に業務を外注する形態が多くなっています。
相続人 ─→ 窓口(銀行、相続センター等) ─→ 外注 (司法書士、税理士、土地家屋調査士等)
この場合には次の料金が必要です
窓口の料金(有料)+各資格者の料金(有料)
※窓口料金は高額(遺産総額の数パーセント・最低50万円以上)となる傾向で、数百万になる場合もあります。
金融機関の相続手続き費用の最低料金(参考)
| 相続手続き最低料金 |
別途請求される料金
相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
不動産相続登記にかかる登録免許税および司法書士報酬
戸籍・除籍謄本、固定資産税評価証明、不動産登記事項証明書等の取り寄せ費用
預貯金等残高証明書発行手数料など |
|
| N銀行 | 50万円(税込) | |
| F銀行 | 110万円(税込) | |
| R銀行 | 110万円(税込) | |
| M信託銀行 | 110万円(税込) |
当事務所の相続手続き代行料金
当事務所は窓口として最初の相談から手続きの終了までお世話させていただきますが、相続に必要な資格を多く保有しており、相続人間で争いがない場合は、ほとんどの手続きを当事務所1か所で行うことが出来ます。
相続人 ─→ 当事務所(司法書士・行政書士) ─→ 連携(土地家屋調査士・税理士・宅建業者等)
当事務所1か所で行うことで相続手続き費用は金融機関等に依頼される場合の半額以下で相続手続き(遺産整理業務)が完了します。
低価格ですが国家資格者の司法書士、行政書士、税理士等が最初から責任をもって最後まで関与することで安心安全の手続きができます。
※相続手続きの難易度、実費の多寡により手続き費用は大きく異なります。
具体的に手続きを依頼される場合は、事前に概算見積もりをご提示します。
(登録免許税、戸籍取寄せ実費、郵送費その他の実費は別となります)